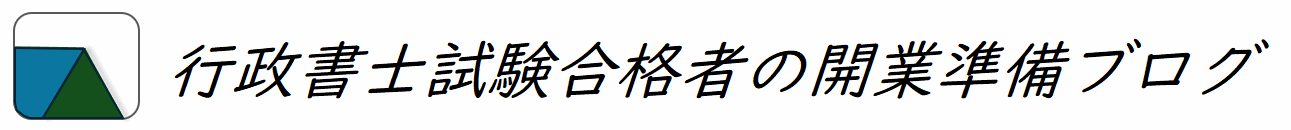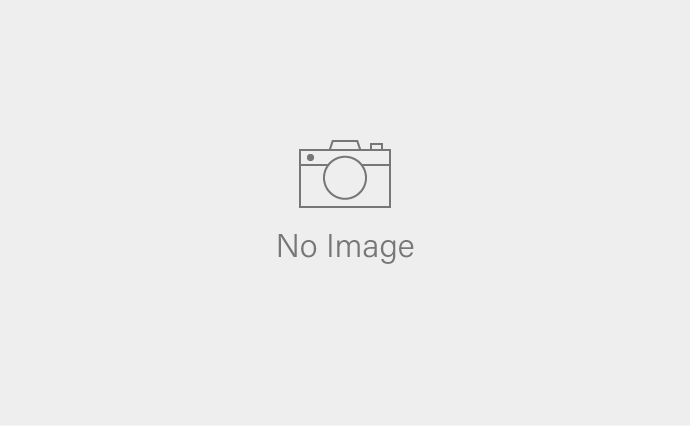民法等の一部を改正する法律案の概要
父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直す民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月17日成立しました(同月24日公布)。この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されますので、来年2026年の5月頃までには施行ということになります。
改正は、共同親権や養育費の履行確保についてをその内容としていますが今日は特に養育費について触れていきたいと思います。
そもそも何歳までが養育費の対象?
法律上に定められた期間があるわけではないですが、20歳までとするケースが多いようです。
ただし、大学進学するなどの場合はその卒業までと合意を取りきめることもあります。
養育費に目安はある?
裁判所のHPに標準算定方式・算定表(令和元年版)が掲載されています。
例として、子1人(0~14歳)の場合で、元夫の給与収入が700万円で元妻の給与収入が100万円のケースだと、月額6~8万円が目安となります。
養育費を払わないとどうなるの?
裁判所所に強制執行の申立てをして、相手の財産等を差し押さえ、強制的に支払わせるという方法があります。
ただし、改正前の現行法だと「債務名義」のない場合には強制執行ができませんので、離婚協議書で養育費の取り決めをしそれを公正証書で作成するなどの必要がありました。
今回の改正により、養育費等の請求権に一般先取特権が付与されることとなり、その一般先取特権を証する文書(当事者間で作成した離婚協議書などでも可)があれば担保権に基づく実行も可能となりました。
また、上記のような離婚協議書や養育費の取り決めがなされなかった場合でも、法定養育費制度が導入されたことにより養育費の請求が可能になります。